子ども成長に「オチンチン力」を・・・すごいタイトルです。
では、早速・・・
オチンチン力
まずは、本の紹介です。
「新 男の子を伸ばす母親はここが違う 松永暢史」
この本に書かれていた言葉。
”男の子の「際限なくチョロチョロする能力」「余計なことをする力」「とんでもないことを思いつく力」のことを「オチンチン力」”
妻から面白いから読んでみてと渡され、笑いながら一気に読みました。(読みやすいので皆さんにもお勧めです。)
うちの息子がまさにオチンチン力が全開だから(笑)
息子のオチンチン力
今、小3(8歳)
この子はやりたいことをする力がすごいんです。
子どもは皆する(?)、ビービー弾集め、変わった石、貝殻、虫を集めたり、春には土筆も大量に集めてくれたりします。
そしてそして、高いところから飛び降りるのを挑戦したり、怪我をして、学校から連絡があることも…。

そして、facebookではお知らせしていますが、うちは先日引っ越ししました。
転校はなく学校は同じなのですが、新しい登校班、ご近所のお友達もまだいない中、
息子は数日でたくさんお友達を作っています。
学校から帰宅してお友達が来て、いっぱい遊んで、バイバイした後、
また違う子がピンポーンときて遊びが開始。
おぬし何者?
学年も性別も関係なく
誘って、断られても、めげない、めげない。
ある時、息子が「どうしたらいいの!?」と何か機嫌も悪い様子です。
聞けば
「AちゃんともBくんとも遊びたいのに、どっちと遊べばいいの?どうすればいいの?」
何それ、贅沢な悩み・・・(笑)
でも、本人はいたって真剣にどうすればいいか考えている様子。
AちゃんとBくんは面識がなく、学年も違う。
そして、悩んだ結果、みんなが友達になって一緒に遊べばいいという結論に。
毎日全力で遊んでいます。すごい!
無から発想するチカラ
ある時、何もない広場で、子どもたちは時間待ちをする必要がありました。
さて、どうやって時間を過ごしたと思いますか?
子どもたちは高いところから飛んで距離を競争したり、相撲を始めたり、靴を飛ばしたり…
「遊びの天才」と思いました。(親バカですみません^^;)
今ゲームがないと遊び方が分からない子が多くありませんか?
学校のテストができても、人間関係がうまくできない、指示されたことしかできない、自立しない、高学歴プア、引きこもりも増えてきていると聞きます。
草食系男子も多いですよね。
その原因は、この幼少期からのオチンチン力がない子、はぐくまなかった、はぐくめなかった子が多いからだそうです。
(実際草食系男子は、男性ホルモン、テストステロンが低いという調査もあるそうです)
人の誘い方がわからない
わからないまま、誘って、断られて、それで人を傷つける、自分を傷つけるという短絡的な人が増えているような気がします。
LINEやゲームのように「ぽちっと」ボタンを押して「すぐに反応がない」「思い通りの反応ではない」とイライラしてしまうのでしょうか。
このオチンチン力の学びは成長してからでは、なかなか身に着けられるものではありません。
大人になると失敗が怖いですからね・・・
関連記事:シュタイナー教育のにじみ絵に参加してきたときのこと。同じようなことを数年前にも書いていました。

私はというと…
私は小さい時、どうしていいか、何をしていいかわからずよく黙っていました。
黙っていると、大人は「静かね、おとなしいね」と褒めているような声をかけてくれていたので、これでいいんだとずっと無口でした。
親に遊園地でも、外食でも、「〇〇したい」「〇〇食べたい」といえず、素直にいえないままでした。兄弟が多いというのもあって遠慮してたのもあります。
そして…、関西だし、友人などの影響もあり
おもろいこと、自分がしたいことを叶える行動ができるようになったのはずいぶん大きくなってから。覚醒するまで長かったです…。
そして、その覚醒するのに「ロルフィング」の影響はとても大きかったです。
自分のことを感じ、知り、行動する。
妻の妊娠出産、子育て、森のようちえんなどを通して「感覚」の大切さ、それを邪魔しないように
出来るだけ見守るということをしてこれたのかなと思います。
とはいえ、口うるさく怒ることもありますが・・・
この本を読んで、もっともっと見守ろうと思います。
子どもの本当に好きは、大人からしたらしょうもないこと
息子は基本ご機嫌で、うるさいくらいしゃべったり、歌っていますが、時々しずかに集中していることがあります。
絵をかいたり、折り紙をしたり、工作、粘土、ラキュー、ブロック・・・
その時はできるかぎり声をかけず見守ろうと親同士、目でサインして十分にやりきらせるように配慮しています。
たとえ就寝時間が遅くなっても・・・(内心はあせってますが、ぐっとこらえて…)
また、成績表やテストの結果をできるだけ見ない、それを見ても「評価しない」「褒めない(けなさない)」と妻と決めています。
(もし100点だったときは、「100点とったんだね」と事実を認めるということはします。100点だから何かご褒美的なことを与えるとか、100点だから、ということはないようにしているということです。それは点が良くないときも同じです。)
だから子どもも成績のために、勉強を頑張ることはしません。
もちろんニガテ、嫌いにならないように勉強をサポートすることもあります。
何より今の時期は頭の勉強より大切なことを学ぶ大切な時期。
子どものやりたいことは、大人からしたらしょうもないこと。
汚いこと、危ないこと、意味のないことかもしれません。
ほんまアホやなぁ、ということ(大阪弁の愛情をもった表現として)
ですが、
やりたいことをやる力=生き抜く力です。
勉強とオチンチン力は反比例ではない
hinataに幼いころから来ているお子さんの話。
すっかり大きくなって、声変わり、有名な学校に入っているそう。
そのお母さんは、ゲームを与えず「本物を体験させる」ということを徹底されていて、一緒に釣り、スキー、山登り、川遊び、音楽、スポーツ…さまざまなことを一緒に取り組まれていました。
入試もこれまでの詰め込み、知識力を重視する時代と違い、思考力、判断力、応用力へと変わっていくとのこと
もちろん塾なども含め勉強のためのサポート、送迎、自然食のお弁当…
きっと大変な毎日。私は真似できないと思います。
だからといってお子さんのために自分を犠牲にしているということでなく、ご自身も趣味も楽しまれていますし、お子さんと感動を一緒に味わいながら「オチンチン力」を高めていっておられます。
それが成長したお子さんにも出ているような気がします。
しっかりお勉強もしながら、心身とも素直にのびのび成長している感じをうけます。
もちろんそのサポートとしてお子さん、ご自身も含めロルフィング、ホリスティックヒーリングを受けられています。
一方、街中、公園でもダメ、汚い、静かに、やめなさい「心身の抑制=逆オチンチン力」で大人のような神経的な緊張、複雑な制限を持つ子も増えてきています(状況によりしつけ、マナーも必要ですし難しいところですけどね)
そんな子どもさんにロルフィング、ヒーリングもサポートとして役立ちます。
それにあわせて親、環境のサポートも大きいかなと思います。
子どもが大きくなるのはアッという間
うちの息子は、身体も小さかったし、言葉も、字を覚えるのも遅かったです。
最近、身長がぐっと伸びてきていて、抱っこもできない重さです。
嬉しさと共にさみしさもあります。
1年生の時は、この世の終わりというぐらい大泣きして帰宅して。
どうした??
捕まえて育てていた「トカちゃん(トカゲ)がいなくなった(逃げた)…」
「・・・」
<ほったらかしにしてたから、とおちゃんが面倒みてたやん^^;>
最近泣くこともへってきました。
子どもはあっという間に大きくなります。
今しかできないこともあるし、hinataには小さい子もロルフィングを受けに来られますが、この
「おチンチン力」
男の子の「際限なくチョロチョロする能力」「余計なことをする力」「とんでもないことを思いつく力」
を育てて欲しいなと想いこちらに本を紹介させて頂きました。
おやつの時間、ゼリーを食べる時
きれいな形のゼリーをわざわざぐちゃぐちゃどろどろにしてから、細いストローでチューチューと
時間をかけて遊び食べをしていても・・・「早く〇〇しなさい!!」という気持ちを抑えて
「オチンチン力・・・」
「オチンチン力・・・」
妻も独り言のように唱えて我慢しています(笑)
大人になってからではできない感動や想い、そこから学べること、発見、発明、気づける何かがきっとあるから・・・
子ども達の成長を見守っていきましょう。
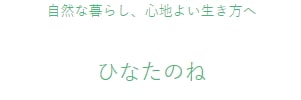


コメント